ブログ、延々と続く話を書き初めてしまった。別の話題で中断することなく、それは別立てにして、延々と続けていこう。延々と続くほうのタイトルは「命綱」だ。どうか続けて読んでください。
前を向いて、下が見えずに錨に到着した。その時に後ろを振り返って進めば、魚礁はすぐに見つかったはずだが、手に持っていた細いロープをアンカーに結んで、そのまま前方にロープを伸ばしながら進んだ。魚礁は見つからない。そんなはずはない。魚探で魚礁の形を確認して居る。ロープを海底にこするようにして左に旋回する。魚礁があれば、引っかかるはずだ。
当時は、残圧計などというものは無い。時計もない。今の良いレギュレーターは、最後まで、同じ呼吸ができるが、その頃のレギュレーターは、空気の残圧が少なくなると、呼吸の抵抗が増す。その呼吸抵抗と時間の感覚で浮上を決める。リザーブバルブという残圧を知らせる装置もあったが、貧乏な僕達の使っているボンベは、消火器改造型で、リザーブバルブはついていない。水深30mではそんなに長くは空気がもたない。そろそろだなと思って引き返した。引き返して錨綱を水面に向かって手繰る。降りる時と全く逆のむきになる。少し進むと真下に魚礁が見えた。
そのまま浮上を続ければ、何事もなかった。しかし、今のようにすぐにタンクに空気が充填できるわけではない。充填したボンベを木枠にいれて、送ったものだ。僕達にはまだ車というものがない。電車で来た。
タンクはこれだけしか持ってきていない。これで、なにもしないで、浮き上がるわけには行かない。ロープの下の魚礁に降りた。
メバルとソイの類がいた。写真を数枚撮った。その時魚礁に膝を突いた。これで、ドライスーツに穴が開いたらしく冷たい水が足に入ってきた。
空気が次第に渋くなってきた。浮上しようとすると足に水が入っていて、浮力を失ってしまっていて、浮かない。フィンで蹴っても、水で膨張しているスーツで満足に蹴れない。なんとか錨綱までたどりついて、この綱を手繰った。
手繰り始めて、空気は完全に無くなって、吸っても来ない。死に物狂い手繰る。浮上速度だとか、息を吐き出しながら上がる、とか、そういう段階ではない。生物として、死ぬのを拒否している。ロープを手繰るのだが、片手には高価な理研のカメラ、未だニコノスが出ない前に、国産で使えるただ一つのカメラで、20万とか、40万とか言われている。今の40万ではない。次の年、卒業した僕が東亜潜水機に入った初任給が9800円だった。9万8千ではない。9千8百円だ。死んでもこのカメラを手放すわけには行かない。
![b0075059_8553117.jpg]()
理化学研究所が作ったカメラ、中にはトプコンという。スプリングモーター巻き上げのカメラが入っていて、先進的なメカニズムだった。
死ぬ寸前、窒息する寸前に水面に顔をだした。
しかし、ドライスーツマスクのガラスを外してもらわなければ、外の空気は吸えない。船に引き上げられてガラスをとってもらった。
もしもこの時に頭上に錨ロープがなかったならば、助かっていない。先生は命綱を付けておけばよかったと思ったに違いない。
そして、僕は東京水産大学を卒業して、東亜潜水機に入る。
そして、「命綱を降ろせ」の100m潜水をやらせてもらう。
東亞潜水機をお世話になったにも関わらず、やめることになり、カメラのハウジングを作ったりしていたが、人工魚礁の調査でなんとか食いつないだ。
その人工魚礁調査でテレビの撮影でライトが必要だ。今は明るいバッテリーライトが各種売られているが、そのころはバッテリーライトといえば、乾電池の懐中電灯のようなもので、とても撮影には使えない。船の上で発電機を回して、1キロワットの有線ライトを使っていた。そのライトを持つアシスタントが必要だった。そのころのスガマリンメカニックの出資者で幼なじみの鈴木博が人工魚礁調査を経験したいという。かれは、日本スキューバ潜水という会社をやっている。今は二代目で立派になっている。
茨城県水産試験場の仕事で「ときわ」という試験場の船で沖にでた。これも30m近い深度で、僕がカメラを構え、鈴木博がライトマンで撮影した。撮影に熱中していると、肩を叩かれた。振り返ると、空気が無いという。もっと前に知らせてくれると良いのに、後で聞けば、撮影しているから、空気が無くなるまでがまんしたという。そんなバカな!、マウスピースを渡した。バディブリージンングである。二回呼吸したら返してくれることになっている。しかし、返してくれない。無理に取り上げると溺れそうだ。ためらうこと無く、僕はマウスピースを戻してもらうことを諦め、彼を抱えて、ライトケーブルをたぐって浮上した。水面にでたときは自分も瀕死状態だった。
![b0075059_857562.jpg]()
人工魚礁撮影調査、これは、もう少し後の写真だが、ライトのスタイルは同じだ。
バディブリージングでマウスピースが戻ってこないことはよくあった話で、そのためにオクトパスができたのだが、ダブルホースではオクトパスは付けられない。そのためにダブルホースが無くなったともいえる。呼吸そのものとか、気泡がマスクの前にでないということではダブルホースの方が優れていたのだが、残圧計も付けられないということで、ダブルは消滅した。
有線ライトケーブルのおかげで助かったと僕は思った。その後は有線ライトを意識して使うようになった。有線ライトを使うためには、ケーブルを操作するアシスタントが必須になる。つまりバディが必須になり助け合うことができる。
現、海洋リサーチの社長である高橋くんもスガマリンメカニック出身だが、彼と、これも茨城で潜っているときに、急潮に出会って、有線ライトの線が切れるかと思うほど引っ張られたが流されなかった。
前を向いて、下が見えずに錨に到着した。その時に後ろを振り返って進めば、魚礁はすぐに見つかったはずだが、手に持っていた細いロープをアンカーに結んで、そのまま前方にロープを伸ばしながら進んだ。魚礁は見つからない。そんなはずはない。魚探で魚礁の形を確認して居る。ロープを海底にこするようにして左に旋回する。魚礁があれば、引っかかるはずだ。
当時は、残圧計などというものは無い。時計もない。今の良いレギュレーターは、最後まで、同じ呼吸ができるが、その頃のレギュレーターは、空気の残圧が少なくなると、呼吸の抵抗が増す。その呼吸抵抗と時間の感覚で浮上を決める。リザーブバルブという残圧を知らせる装置もあったが、貧乏な僕達の使っているボンベは、消火器改造型で、リザーブバルブはついていない。水深30mではそんなに長くは空気がもたない。そろそろだなと思って引き返した。引き返して錨綱を水面に向かって手繰る。降りる時と全く逆のむきになる。少し進むと真下に魚礁が見えた。
そのまま浮上を続ければ、何事もなかった。しかし、今のようにすぐにタンクに空気が充填できるわけではない。充填したボンベを木枠にいれて、送ったものだ。僕達にはまだ車というものがない。電車で来た。
タンクはこれだけしか持ってきていない。これで、なにもしないで、浮き上がるわけには行かない。ロープの下の魚礁に降りた。
メバルとソイの類がいた。写真を数枚撮った。その時魚礁に膝を突いた。これで、ドライスーツに穴が開いたらしく冷たい水が足に入ってきた。
空気が次第に渋くなってきた。浮上しようとすると足に水が入っていて、浮力を失ってしまっていて、浮かない。フィンで蹴っても、水で膨張しているスーツで満足に蹴れない。なんとか錨綱までたどりついて、この綱を手繰った。
手繰り始めて、空気は完全に無くなって、吸っても来ない。死に物狂い手繰る。浮上速度だとか、息を吐き出しながら上がる、とか、そういう段階ではない。生物として、死ぬのを拒否している。ロープを手繰るのだが、片手には高価な理研のカメラ、未だニコノスが出ない前に、国産で使えるただ一つのカメラで、20万とか、40万とか言われている。今の40万ではない。次の年、卒業した僕が東亜潜水機に入った初任給が9800円だった。9万8千ではない。9千8百円だ。死んでもこのカメラを手放すわけには行かない。
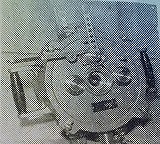
理化学研究所が作ったカメラ、中にはトプコンという。スプリングモーター巻き上げのカメラが入っていて、先進的なメカニズムだった。
死ぬ寸前、窒息する寸前に水面に顔をだした。
しかし、ドライスーツマスクのガラスを外してもらわなければ、外の空気は吸えない。船に引き上げられてガラスをとってもらった。
もしもこの時に頭上に錨ロープがなかったならば、助かっていない。先生は命綱を付けておけばよかったと思ったに違いない。
そして、僕は東京水産大学を卒業して、東亜潜水機に入る。
そして、「命綱を降ろせ」の100m潜水をやらせてもらう。
東亞潜水機をお世話になったにも関わらず、やめることになり、カメラのハウジングを作ったりしていたが、人工魚礁の調査でなんとか食いつないだ。
その人工魚礁調査でテレビの撮影でライトが必要だ。今は明るいバッテリーライトが各種売られているが、そのころはバッテリーライトといえば、乾電池の懐中電灯のようなもので、とても撮影には使えない。船の上で発電機を回して、1キロワットの有線ライトを使っていた。そのライトを持つアシスタントが必要だった。そのころのスガマリンメカニックの出資者で幼なじみの鈴木博が人工魚礁調査を経験したいという。かれは、日本スキューバ潜水という会社をやっている。今は二代目で立派になっている。
茨城県水産試験場の仕事で「ときわ」という試験場の船で沖にでた。これも30m近い深度で、僕がカメラを構え、鈴木博がライトマンで撮影した。撮影に熱中していると、肩を叩かれた。振り返ると、空気が無いという。もっと前に知らせてくれると良いのに、後で聞けば、撮影しているから、空気が無くなるまでがまんしたという。そんなバカな!、マウスピースを渡した。バディブリージンングである。二回呼吸したら返してくれることになっている。しかし、返してくれない。無理に取り上げると溺れそうだ。ためらうこと無く、僕はマウスピースを戻してもらうことを諦め、彼を抱えて、ライトケーブルをたぐって浮上した。水面にでたときは自分も瀕死状態だった。

人工魚礁撮影調査、これは、もう少し後の写真だが、ライトのスタイルは同じだ。
バディブリージングでマウスピースが戻ってこないことはよくあった話で、そのためにオクトパスができたのだが、ダブルホースではオクトパスは付けられない。そのためにダブルホースが無くなったともいえる。呼吸そのものとか、気泡がマスクの前にでないということではダブルホースの方が優れていたのだが、残圧計も付けられないということで、ダブルは消滅した。
有線ライトケーブルのおかげで助かったと僕は思った。その後は有線ライトを意識して使うようになった。有線ライトを使うためには、ケーブルを操作するアシスタントが必須になる。つまりバディが必須になり助け合うことができる。
現、海洋リサーチの社長である高橋くんもスガマリンメカニック出身だが、彼と、これも茨城で潜っているときに、急潮に出会って、有線ライトの線が切れるかと思うほど引っ張られたが流されなかった。