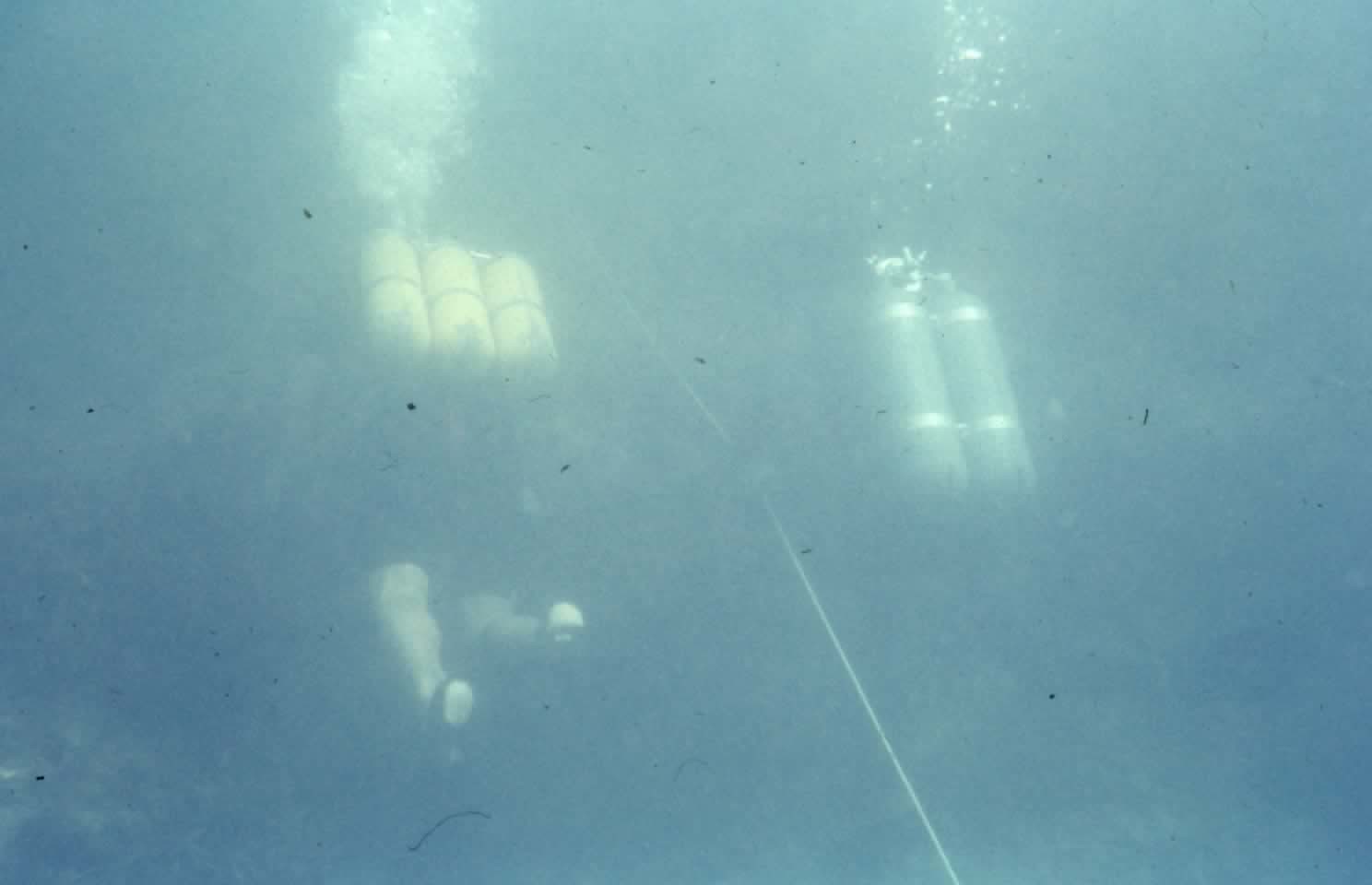
1957年の潜水実習が僕の本格的ダイビングの第一歩だった。そして、1954年、日本での学生スクーバ潜水実習のはじまり,そして、日本初のスクーバダイビング死亡事故が起こる。日本のスクーバダイビングの原点であると同時に、死亡事故の原点でもある。
そして、1957年、自分たちの受けた講習は、命を落とすような危険は一つもなかった。たとえ水中脱着で、ウツボの上に手を突いたとしても、命を落とすような事故にはならない。1954年に、なぜ事故が起こったのだろう。なぜ、どうしてそんなことになったのだろう。原因は?、そして経過は?、考え始めたのが、1957年の実習の時だった。
その後もずっと考え続けた。もちろん1954年の事故のことだけではない、それが始まりで、次々と起こる事故について考えた。そして、そのなぜ、どうして、を考えることが、安全に繋がるとも意識して考えた。以後、無数、数えられないほど、危ないことをしている。そして、それが危ないことだったと知ること,知覚することで、危険を少なくとも命を落とすことを回避してきた。
自分に起こったこと、自分の眼前で起こることは、回避できる。しかし、自分のことではなく、自分が居ない場所で起こることは回避できない。しかし、自分の考えを伝えることで、回避できるのではないか?そんな考えに到達するのは、ずっと後、1960年代の終わりころダイビングの指導を仕事の一つとするようになってからだが、1957年に1954年の事故のことを考えたのがその始まりであった。
ダイビングの歴史について書こうと資料集めをして、まず、事故の歴史を書こうとブログに書き始めたのが、2018年2月7日、「スクーバダイビング事故の歴史」の第一回で、当然のように1954年の本邦初の事故について書いている。
まずは、2018年 2月 7日 のブログを若干の修正をしてここに載せる。
スクーバダイビング事故の歴史(1)1954
事故のあった講習での指導教官は、ダイビングの講習も卒業論文も、さらに就職もお世話になった恩師である宇野寛先生(後に名誉教授)であるが、1957年の実習の際に、この事故について言及されることは無かった。
さらに、不遜な事をいえば、1954年の事故について、きちんとした報告書として、残してほしかった。
文章として残すことが、経験の共有になり、それを知識という。
1954年の事故は報告書が無いので、ここでは、断片的に先生に聞いたこと、また実習場の古川技官に質問して、これも断片的に聞いたことなどを総合した類推を書く。類推であり、正確ではありえないし、1957年ごろにした類推であり、それから64年の歳月が経っているが、これはこれで、一つの報告ではある。
まず、事故はダイビング講習が終了した後に起こった。宇野教官は現場にはおられなかった。講習中であれば、指導教官の先生の不在はありえない。死亡したのは旭さん伊藤さんの二名で、実習が行われた実習場前の入り江で、エントリー場の小さな桟橋から沖に向かった。誰がどこから見ていたか不明だが、見ていると一人が浮上して、助けを求めるように手を振った。その後沈んでしまい、見ていた者が異常を感じで小舟を出し潜ってみたところ、二人を発見し引き上げたが蘇生しなかった。
二人が何の目的で、何をしていたのかわからない。一つは、実習に使用したロープの片付け撤収、何か探し物をしていたのかも知れない。あるいは、何か理由をつけて、遊び的な体験ダイビングをしていた。この二人は泳力抜群で、実習の成績はトップであったという。ロープの撤収であれば、小舟が追従して引き上げなどを行うだろうから、片づけとは考えにくい。が、考えにくいことをやっていたかもしれない。
とにかく、二人はバディを組んでおり、そのうちの一人が浮上して救助を求めている。当時、事故原因は、息を止めての急浮上による空気塞栓だとも言われたが、実習の初めから、息を止めての浮上は固く戒められており、二人が連続して肺破裂をするとは考えられない。なお、解剖所見などは公表されていない。
この事故は学校側の刑事責任が問われる裁判になっていて、現場の責任者である、宇野講師(当時)が矢面にたっていた。
刑事裁判が続行中であるにもかかわらず、1956年に実習が再開された恩恵で僕は、1957年に実習を受けることができたのだが、当事者であった宇野寛先生の心労は大きなものであったとだろう。しかし、その心労を私たちに語られたことは無かった。これも、語られた方が良かったと思う。
責任追求の具体点は、小舟のサジッタが頭上の水面に居なかったことであったと聞く。そして、僕の四年次に先生に聞いた範囲では、無罪となり、「疑わしきは罰せず、だよ」と、嬉しそうに語ってくれた。事故について、先生が語ったのは、この一言だけだった。
自分についていうと、バディが居たからと言って事故を防げない場合もある。頼りになるのは、頭上に置くボート、小舟である。出来うる限り、小舟、ゴムボートを置くようにしようと考えるようになった。以後、何回か、頭上に置いた小舟で事故が大事に至らなかった経験がある。陸上からエントリーできるということは、スクーバの大きな有利点であるのだが、それがために起こった事故が多い。陸上からのエントリーによる事故の大半は、ボートが頭上にあれば助かっただろう。日本初の事故と同じことだ。
★☆
これが、2018年 2月 7日 のブログだが、一読して、報告として不十分である。何も、事故が起こった時点のことは、書いていない。これとは別に、1957年の実習について書いているが、常に上にはサジッタ(櫓漕ぎの小舟)が居た。これは、この1954年の反省の上でのことだろう。そして、このこと、小舟の使用など、潜っているダイバーと水面上、水上との連携は、ここから先の「ダイビングの歴史・事故について」でも繰り返し出てくるメインテーマでもあるのだが。
1954年の講習には、僕を1956年に奄美大島に連れて行ってくれ、そして、以後も親交が続いている白井祥平先輩が参加している。もちろん、折にふれて、事故が起こった時のことを聞いてはいたが、あいまいな答えしか返ってこない。誰でも事故の詳しいことは語りたがらない。僕も強くはお願いしなかった。
しかし、お互いに80を超え、ダイビングの歴史を書き始めた。1964年、その第一歩でダイビング事故死を出したということは、歴史の重大な1ページだ。強く、教えてくれるようお願いした。
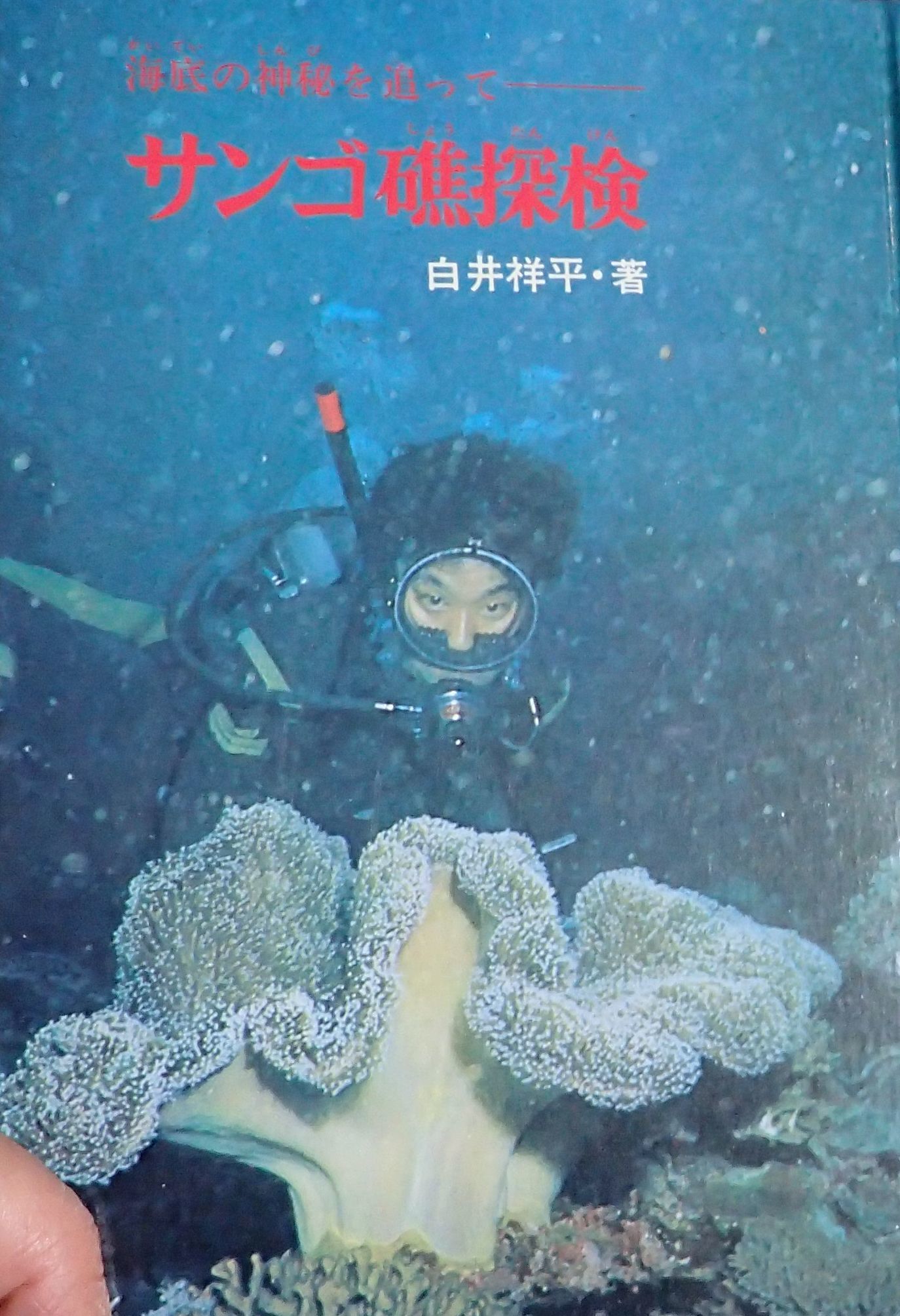
そうしたら、驚いたことに、白井先輩はこの事故のことをすでに本に書いていて、その本をいただいて来た。
1975年発行「現代こどもノンフィクション「サンゴ礁探検」白井祥平 あかね書房」である。
白井先輩はほとんど無数と思われるほど本をかいておられる。それらの本のほとんどは、自分も持っていて、書棚の一列は、白井先輩の本で埋まっているが この本を持っていなかった。こども向けだから、と買わなかったのだろう。読んでみると、1956年の奄美大島探検のことも書かれている。
以下は、「サンゴ礁探検」白井祥平著からの書き抜きである。
「アクアラングと言う名称でこの潜水機がはじめて日本にお目見えしたのは1953年のことでした。アメリカの地質学者、ロバート・ディーツ博士が持ち込んできたのですが、
わたしはそのとき、たまたま大学の実習で小湊に滞在していました。
仲間たちと小舟に乗って見学にでかけましたが、この時の印象は忘れることができぬほど強烈なものでした。
見るからにスポーティで軽そうなゴム製のマスクやフィンを着け、ボンベを背負って海に飛び込む博士の姿は、わたしには英雄のように見えました。
小湊でのスキューバ潜水を見学した翌年、二台のスキューバが水産大学に輸入され、日本で初めてこの機械を使っての潜水を体験することになりました。
潜水を習う学生は13名、機械は2台しかないので、A班とB班の二班に分かれて交代で練習することになり、わたしは A 班の班長になりました。
実習はマスク式潜水を使う潜水と、スキューバをつかう二通りを行うことになっていました。
が、マスク式潜水による潜水を早く終えてスキューバでの潜水をと、だれもがスキューバを背負うのを待ちかねていました。
いよいよ、スキューバによる潜水実習が始まりました。
わたしたちは機械に使い方を教わったあと、最初の練習はロープを伝わって海底までもぐり、また帰ってくるというたいへん簡単なものでした。
わたしの番がきました。重いボンベを背負い、大きなフィンを履きました。そして腰になまりの錘をつけて潜水台にたったときには、なんだかこの世もこれでお別れのような不安を感じました。ところがいざ海中にはいってみるとそんな不安は一ぺんにどこかに吹っ飛んで、もう、あたりの景色を見るのに夢中になっていました。
4m、5m、深くなるにつれて耳が痛くなります。水深計を見ると、8mをさしています、あ、ここで耳抜きをするのだな。
すばやく唾をのみこむと、ぷすんと音がして、急に耳が軽くなり、痛みが感じられなくなりました。きれいだな。なんというすばらしさなんだろう。
ゆっくりと海中をみたこの最初の体験は、「すばらしい」という一語につきました。この時の感動は、その後何年も、ずうっと海に潜り続けているわたしの心に消えずにのこっているのです。
いったい何分間海中にいたのか、潜水台にあがったときにはわかりませんでした。
午前中の初潜水を終えた私たちは、ただ興奮して、思い思いに感想をはなしあいました。そして昼休みも早々に切り上げ、再び潜水台にもどるのでした。
「今度は、ロープをもっと深いところまでおろしてみよう。」
午後からは20mの深さまでロープを沈めて潜水することになり、その作業を元気者の旭君と伊東君が受け持つことになりました。
(今度は、できるだけ長い時間、潜っていよう)
海面から消えていくふたりを見送りながらわたしはそう思いました。
ふたりがロープを持って潜水している間、二回目の潜水に思いを馳せていたせいか、作業の時間がすこしかかりすぎているのに誰もきがつきませんでした。
(ちょっとおそいな)
何気なく時計を見たわたしは、もう10分もすぎていることに気づきました。しかし、だれもふしぎに思わぬようなので、(きっと作業を終えて、あたりを散歩でもしているのだろう。なあに、大丈夫)と私はむりに気持ちをおちつかせるようにあたりをみまわしました。
すると、今まで笑い声を出していた仲間たちも、顔を見合わせ、何か不吉な予感にでもおそわれたように、海面をながめてているではありませんか。
「あっ、あれは!」
ちょうどそんなとき、100mほど沖合に一人が浮上しました。手を振っていますが、マスクをつけているので、どちらかを見分けることはできません。ただ、異常事態が起きたようにもみえなかったので、私たちはほっとして合図を送りました。するとまた彼はもぐってしまいました。
「あれは、旭と伊藤のどっちだろう。」
「ずいぶん遠いところで遊んでいるな」
などと話し合いながら、私たちは二人の帰りをまちわびました。
ところが再び姿をあらわしたのは、さきほどよりもずっと遠い、はるか沖合いだったのです、おまけに今度は、事態が切迫しているのか手のふりかたがおかしいのです。
「これはいかん!すぐ救援だ!」
宇野教官は、真っ先にロープを持って飛び込みました。
はじかれたように立ち上がった私たちは、一斉に行動を起こしました。あるものは連絡船の現場への急行を頼みに行きます。

※ 事故当日、事故直前に取った記念写真。潜水台の上である。遠景に見える柱は、実験場禁漁区の境目を示す柱である。海は凪であり静かである。
左端と右端が亡くなった旭さん、伊藤さん、右から4人目、前列が白井先輩、左から3人目キャップをかぶっているのが猪野峻先生であり宇野先生の姿はない。
宇野先生は、写真・現場にいな。なのになぜ、ロープを持って飛び込んだのが、宇野先生なのだろう。宇野先生は、記念写真を撮ったときはまだ、現場に来られていなくて、所用で遅れたのだろうか?
あたりの岩場に散らばっている非常用のロープを集めて次々と仲間に渡しました。一本のロープでは短くて、次々とロープをつながなければとても遠くて届かないからです。
「がんばれ、たのむぞ」仲間たちは飛び込んでいきます。
「あっ、浮いたぞ、もっと沖の方だ。」
はるかかなたに見え隠れするように浮上したのは、旭君か伊東君かまたくわかりません。一回目の浮上から、すでに5分も経っています。はらはら見守るうちに、ようやく連絡船が到着し、先頭の泳者がしっかりとダイバーのからだを抱き抱えるのが見えてほっとしました。
※連絡船とは、小湊水族館(実習場)と対岸の鯛の浦を結んでいる渡し船で、実習場の小突堤が船着き場になっている。
しかし、まだもう一人の友人が発見されていないのです。万が一を考えて頼んだ本職の潜水夫や医師も到着しました。
私たちは潜水夫に海中の探す場所を教え、その方は本職に任せて、たった今陸上に担ぎ上げられた旭君の救助に全力をあげるようにしました。
旭君は呼吸もとまり、仮死の状態でした。私たちは交代で必死になって人工呼吸を続けました。
しかし、そのかいもなく、午後九時旭君は帰らぬ人となってしまいました。そして、伊藤君も後から死体となって発見されたのでした。
この事件以来、私たちは多くのことを学びました。ダイビングはたとえ現在のように器械が改良され、潜水技術が普及したとしても、いつも「死」に直接つながっていると考えなければいけないということです。陸上と条件がちがう海中では、あらゆることに注意し、いつも初心者の心構えを忘れては行けないと言うことを私は肝に命じました。」
以上、白井祥平先輩の著書からの抄録 書き写しだが、事故直前の写真に写っていた猪野峻先生は、事故の時、どうされたのだろう。
猪野先生は、アワビについての研究権威者で、学者としては、最高のダイビングの達人であり、後述する日本ダイビング協会を設立する。僕は、ずいぶんとお世話になった。
疑問点はいくつかあるが、正規の報告書ではないし、この場の雰囲気をよくとらえていて、知りたいことはすべて書かれている。
そして、2018年に書いた、事故状況とはまるでちがっていた。まず、1954年の事故は、講習の最終日、あるいは、講習が終わってからの出来事だと思っていた。講習の初日から、二人が沖に向かって泳ぎ出るなど、想像できなかった。
講習の初日に20mを目指すとは、無謀だというのは容易いが、元来、水に潜る行為、しかも命綱をつけないで、糸の切れた凧の状態で、水に潜ること、そのものがすでに無謀なのだ。そして、この事故は、ロープラインを引こうとする潜水であり、二人がロープを手にして水に入っている。水面、水上で監視する者にとって、二人がロープを手放すことは想定していない。ロープを持っているから安心だと思う。
今現在、2022年、ほとんど100%のスクーバダイバーはロープなど持たないで潜降していく。
だから、ロープを持って行かせれば安心と思うだろう。しかし、ロープは手放してしまう。身体に結び付けて置けば安心だろう?。人は、ダイバーは、結び付けたロープをほどいてしまう。また、身体にロープを結び付けるのは、拘束の危険があるので、ロープを身体に結び付けてはいけないと書いてあるテキストもある。ロープラインを張ることが、目的の潜水だから、手に持つのが自然であり、この潜水が危ないなどと思った者はいなかっただろう。
マスク式の送気ホースならば、ホースを切って出て行くことはない。そう、それまでの潜水実習のようにマスク式であれば、スクーバさえ使わなければ、この事故は起こらなかった。
ロープは手放すなどとは、誰も考え間しなかった。ロープを持たせていれば、安心と考えて不思議はない。だから、講習の初日であっても、泳ぎの達者な二人ならば、ロープを持たせて、ロープを海底に引くために潜水させて、不思議ではない。
また、水産大学の潜水実習というのは、現今のレジャーダイバーのCカード講習とは違う。自分もそうだったが、「命がけ」という考えが頭の隅にある。命を賭けてもぐるのだ。そんな風潮の中で、実習が行われる。だからこそ、慎重に行わなくてはならないのだが、それは、後から言うことで、自分も、ここから先に書いて行くのだが、同じような突撃をしている。
だから、現場責任者であった宇野先生、そして、現場にいた猪野先生も責めることはできない。ただ、不満を言えば、事故の報告をきちんと公表してほしかった。事例として、その時の状況を話して、教えてほしかった。
講習に参加した白井先輩の視点から書いたものと、責任者の宇野先生の書かれたもの(書かれなかったが)とは、違ったものであろう。
事故の原因だが、これはもちろん想像だが、20mまで行こう、ラインを引こう、ロープを一杯延ばしても、20mに到達しなかったのだろう。しかし、当時は水深計は持っていなかったから、20mがどこかわからなかったはず。適当なところで戻ればよかった。とにかく、ロープを一杯延ばしても、足りないと思ったのだろう。どんどん先に行ってしまった。一人が、止まって待っていたけれど、戻ってこない。浮上して見たが、水面でも見当たらない。再び探しに潜って行った。
これが、事故に至る経過の想像である。
結果として、もしかしたら肺破裂かもしれないし、溺水だったかもしれない。しかし、それは結果であって、大事にしたいのは、経過と原因(計画:この場合は、20mまで行こう)である。
もしかして、いや、多分、その時の講習生、白井先輩も含めて、宇野先生、猪野先生らとは、話し合いが持たれたのだろう。それを、1957年講習組の僕らは知らせてもらえなかった。知らされていたら、その後の自分たちの潜水もちがったものになっただろう。今の言葉で言えば、情報の共有である。そのために今、ずいぶんと時間が経過したがこれを書いている。
知らせてもらえなかったが、その反省と、その後の研究、によって、1957年の講習のプログラムは作られたと思う。ラインは、潜水台から内側、突堤に向けて引かれ、潜水台から外に向かわなかった。サジッタは何時も真上の水面に居た。そのことが、当たり前に感じていた自分には、講習の初日に、ロープを持っていたにせよ外に向かって泳ぎ出るなどとは、想像もできなかったのだ。