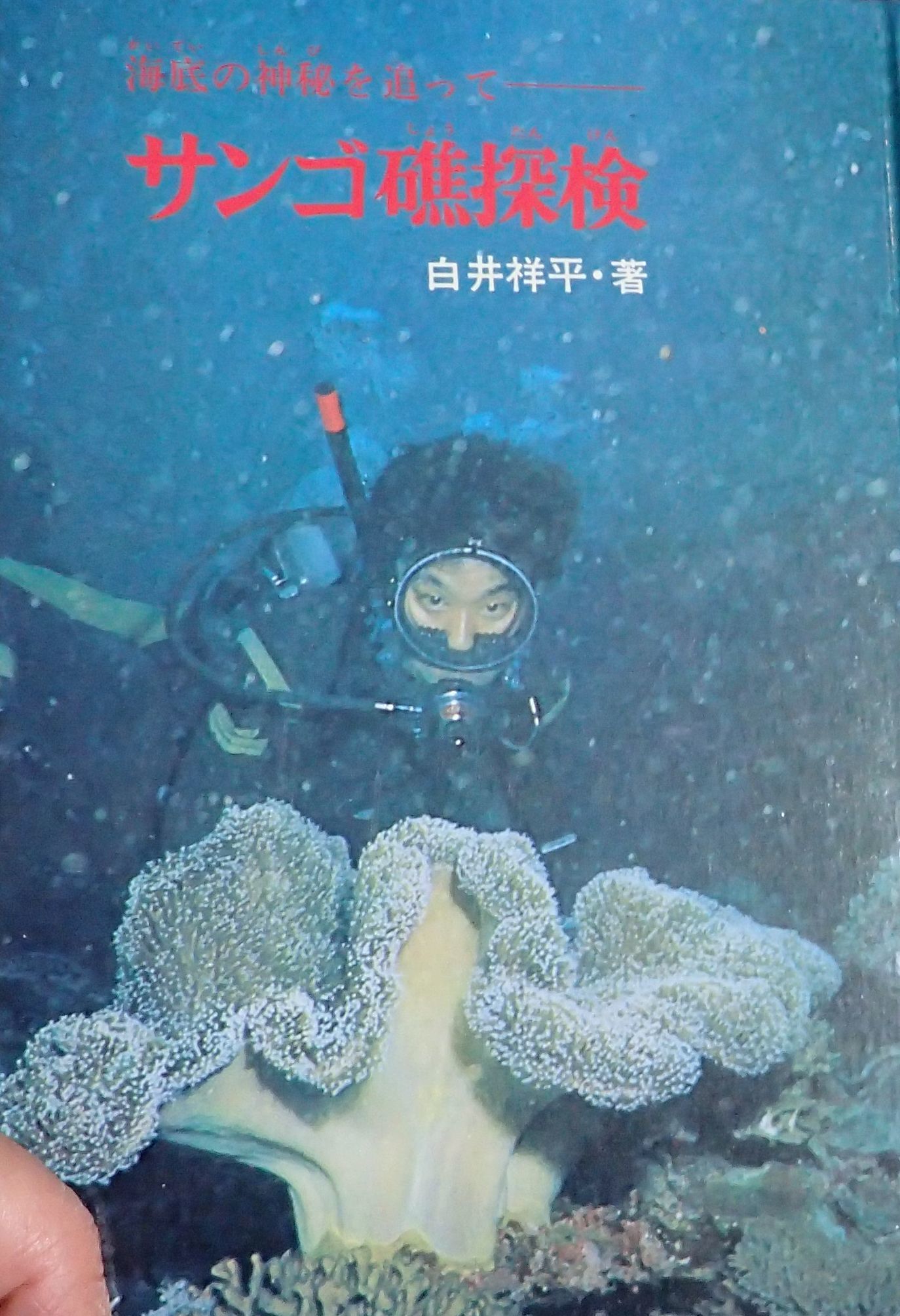以下は、1975年発行の 現代こどもノンフィクション「サンゴ礁探検」白井祥平著からの書き抜きである。
アクアラングと言う名称でこの潜水期がはじめて日本にお目見えしたのは1953年のことでした。アメリカの地質学者、ロバート・ディーツ博士が持ち込んできたのですが、千葉県の小湊の海で初めて実験潜水が行われたときには大騒ぎになりました。 小湊は鯛の浦があり水面から鯛が観られるので有名なところですが、潜水実験をしたために、鯛が浮かんでこなくなったからです。 わたしはそのとき、たまたま大学の実習で小湊に滞在していました。 仲間たちと小舟に乗って見学にでかけましたが、この時の印象は忘れることができぬほど強烈なものでした。 見るからにスポーティで軽そうなゴム製のマスクやフィンを着け、ボンベを背負って海に飛び込む博士の姿は、わたしには英雄のように見えました。 小湊でのスキューバ潜水を見学した翌年、二台の小さなスキューバが水産大学に輸入されたのです。そして、私たちが丁度潜水実習を受ける年に当たっていたので、日本で初めてこの機会を使っての潜水を体験することになりました。
※水産大学に来たアクアラングは2台だけだった。空気を充填するコンプレッサーは、空冷のインガーソルで、1本を充填するのに1時間あまりかかった。120キロならば40分あまりだったから、たいていの場合、120キロで止めた。また、そのころの国産のボンベ、マンガンスチールは重点圧120キロだった。今でも、広島大学の豊潮丸は、120キロまでの充填ですませる。120キロがコンプレッサーのパフォーマンスが良いのだ。
今、レジャーダイビングでは、ナイトロックスなど普通に使うようになったが、学術研究の世界でのスクーバダイビングは、充填圧120キロの空気なのだ。
潜水を習う学生は13名、機械は2台しかないので、A班とB班の二班に分かれて交代で練習することになり、わたしは班の班長として7名の仲間たちと、はやる心を押さえて実習の日をまちました。 わたしはこれまで水中マスクをつけて何十回、いや何百回となく海に潜ってきましたが、しかし、いずれも一回に30秒という短い時間しかもぐることはできませんでした。 でも、今日の実習はちょっと違います。 実習はマスク式潜水を使う潜水と、スキューバをつかう二通りを行うことになっていました。 が、マスク式潜水による潜水を早く終えてスキューバでの潜水をと、だれもがスキューバを背負うのを待ちかねていました。
※マスク式は、空気嚢をつけている旭式で、張り出した磯根の上にコンクリートで8畳敷ほどの平坦な台地(潜水台と呼んだ)をつくり、その上に空気ポンプを置いて、ホースでマスクに空気を送る。アクアラングがくる前、1953年まで、水産大学の潜水実習は、このマスク式だけだった。空気に制限がないこと、ホースにつながれていて安全で、耳抜きとか、潜水の初歩的なことを実習できる。
いよいよ、スキューバによる潜水実習が始まりました。 わたしたちは機械に使い方を教わったあと、最初の練習はロープを伝わって海底までもぐり、また帰ってくるというたいへん簡単なものでした。 わたしの番がきました。重いボンベを背負い、大きなフィンを履きました。そして腰になまりの錘をつけて潜水台にたったときには、なんだかこの世もこれでお別れのような不安を感じました。ところがいざ海中にはいってみるとそんな不安は一ぺんにどこかに吹っ飛んで、もう、あたりの景色を見るのに夢中になっていました。 4m、5m、深くなるにつれて耳が痛くなります。水深計を見ると、8mをさしています、(あ、ここで耳抜きをするのだな。) すばやく唾をのみこむと、ぷすんと音がして、急に耳が軽くなり、痛みが感じられなくなりました。(きれいだな。なんというすばらしさなんだろう。) ゆっくりと海中をみたこの最初の体験は、「すばらしい」という一語につきました。この時の感動は、その後何年も、ずうっと海に潜り続けているわたしの心に消えずにのこっているのです。 いったい何分間海中にいたのか、潜水台にあがったときにはわかりませんでした。 午前中の初潜水を終えた私たちは、ただ興奮して、思い思いに感想をはなしあいました。そして昼休みも早々に切り上げ、再び潜水台にもどるのでした。 「今度は、ロープをもっと深いところまでおろしてみよう。」 午後からは20mの深さまでロープを沈めて潜水することになり、その作業を元気者の旭君と伊東君が受け持つことになりました。(今度は、できるだけ長い時間、潜っていよう) 海面から消えていくふたりを見送りながらわたしはそう思いました。 ふたりがロープを持って潜水している間、二回目の潜水に思いを馳せていたせいか、作業の時間がすこしかかりすぎているのに誰もきがつきませんでした。 (ちょっとおそいな) 何気なく時計を見たわたしは、もう10分もすぎていることに気づきました。しかし、だれもふしぎに思わぬようなので、(きっと作業を終えて、あたりを散歩でもしているのだろう。なあに、大丈夫)と私はむりに気持ちをおちつかせるようにあたりをみまわしました。 すると、今まで笑い声を出していた仲間たちも、顔を見合わせ、何か不吉な予感にでもおそわれたように、海面をながめてているではありませんか。 「あっ、あれは!」 ちょうどそんなとき、100mほど沖合に一人が浮上しました。手を振っていますが、マスクをつけているので、どちらかを見分けることはできません。ただ、異常事態が起きたようにもみえなかったので、私たちはほっとして合図を送りました。するとまた彼はもぐってしまいました。 「あれは、旭と伊藤のどっちだろう。」 「ずいぶん遠いところで遊んでいるな」 などと話し合いながら、私たちは二人の帰りをまちわびました。 ところが再び姿をあらわしたのは、さきほどよりもずっと遠い、はるか沖合いだったのです、おまけに今度は、事態が切迫しているのか手のふりかたがおかしいのです。 「これはいかん!すぐ救援だ!」 宇野教官は、真っ先にロープを持って飛び込みました。 はじかれたように立ち上がった私たちは、一斉に行動を起こしました。あるものは連絡船の現場への急行を頼みに行きます。

※ 2018年、白井先輩を訪ねて、事故当日、事故直前に取った記念写真をいただいてきた。潜水台の上である。左端と右端が亡くなった旭さん、伊藤さん、右から4人目、前列が白井先輩、左から3人目キャップをかぶっているのが猪野峻先生であり宇野先生の姿はない。 宇野先生は現場にはいないはず、なのになぜ、ロープを持って飛び込んだのが、宇野先生なのだろう。宇野先生は、記念写真を撮ったときはまだ、現場に来られていなくて、所用で遅れたのだろう? ※そのころ、小湊実習場は、小さい水族館になっていて、当時としては立派な観光施設です。湾の対岸は日連上人が生まれたと言われる誕生寺があり、誕生寺の沖では、上人の誕生を祝って、めでたい、と鯛が水面で跳ねたといわれる鯛の浦があり、観光船がその上に行って船縁をたたくと鯛が出てきます。そのご観光客が餌をやるのですが、これはいわゆる音響馴致と呼ばれる餌付けなのですが、誕生寺と対岸の水族館を結ぶ観光の通船があり、その舟が水族館側、こちら側に来ていたらしい。
あたりの岩場に散らばっている非常用のロープを集めて次々と仲間に渡しました。一本のロープでは短くて、次々とロープをつながなければとても遠くて届かないからです。 「がんばれ、たのむぞ」仲間たちは飛び込んでいきます。 「あっ、浮いたぞ、もっと沖の方だ。」 はるかかなたに見え隠れするように浮上したのは、旭君か伊東君かまたくわかりません。一回目の浮上から、すでに5分も経っています。はらはら見守るうちに、ようやく連絡船が到着し、先頭の泳者がしっかりとダイバーのからだを抱き抱えるのが見えてほっとしました。 しかし、まだもう一人の友人が発見されていないのです。万が一を考えて頼んだ本職の潜水夫や医師も到着しました。 私たちは潜水夫に海中の探す場所を教え、その方は本職に任せて、たった今陸上に担ぎ上げられた旭君の救助に全力をあげるようにしました。 旭君は呼吸もとまり、仮死の状態でした。私たちは交代で必死になって人工呼吸を続けました。 しかし、そのかいもなく、午後九時旭君は帰らぬ人となってしまいました。そして、伊藤君も後から死体となって発見されたのでした。 この事件以来、私たちは多くのことを学びました。ダイビングはたとえ現在のように器械が改良され、潜水技術が普及したとしても、いつも「死」に直接つながっていると考えなければいけないということです。陸上と条件がちがう海中では、あらゆることに注意し、いつも初心者の心構えを忘れては行けないと言うことを私は肝に命じました。」