機械、道具の類は、シンプルな方が良い。simple is best であると習った。ただし、その用途、目的を完全に果たすことができればであるが。シンプルな方が故障が少ないし、価格も安くできる。修理も容易であり運用の費用も少なくて済む。
しかし、多くの機械、道具の進歩の方向は複雑化である。潜水機も同様で、エレクトロニクス、電子化、そして精密化である。そして、その安全保持といえば、精密化された道具が壊れた時に、予備的に使うシンプルな道具にたよる。つまり呼吸期供給を二つの経路から供給する、ツーウエイに頼る。現代のもっとも進んだ潜水機が安全である理由は、二つの方法で呼吸気体の供給を受けられるからである。
機材は複雑化し、高価になり、複雑化しただけ故障の可能性が高くなり危険度が増す。そしてどんどん重くなる、複雑化と重量は正比例する。
今、スポーツリブリーザーが注目を集めている。僕が手に取ってみたのは一種類だが、やがてもう一種類、さらに増えてゆくと思う。それぞれ高価であり、危険については、二つの給気原を持って行くから、安全性は低くないが、重くなり、高価である。例えば、今、40mにスポーツリブリーザーで潜ろうとする。機材とメンテナンス費用、手間、どのくらいかかるのだろう。機材の購入費まで含めれば、年間およそ100万をダイビングのために使える人でないと、できないだろう。僕が、今度のGWに大瀬崎に行くけれど多分、40mまで潜ると思う。普通の空気のスクーバで潜る。それと、スポーツリブリーザーで潜るのとの差は、多分、無減圧で潜れる時間の差だけだろう。僕のオープンサーキットでの40mは、タッチアンドゴーであり、それで良い。
スポーツリブリーザーに反対しているのではない。複雑なシステム、複雑な機構を使いこなすことは、とても面白いし、それは、ダイビングの楽しみの重要な要素であるから、それで良い。つまり、遊びとして楽しく面白い。しかしプロのダイバーが、この機材を仕事に使うことは決してないだろう。だからスポーツリブリーザーなのだ。
プロのダイバーがリブリーザーを使うとすれば、水深60m以上に潜ろうとする時、例えばオープンサーキットのタンクを5本抱えて行くよりは、軽くて、経済性も高いからだ。しかし、それにしても、60mより深く潜る仕事としても、リブリーザーが費用対比効果があるのは、やはり特別なさつえいとか、特別な仕事である。しかし、その特別な仕事でも今のリブリーザーの使い方は、やはりプロ(作業)向きではない。そのことについては、考えがあるので、そのうちに実験してみたいができるかどうか疑問?
プロの潜水機としては、やはり、使用する目的が効率的に達成できて安全性が保たれるならば、シンプルな方が良い。
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
つい最近に紹介したが、インドネシアの海鼠採り漁師は、マスクにホースを突き刺しただけというこれ以上簡単な潜水機はないというくらいシンプルな潜水機を使っている。これで、小さなコンプレッサーと予備タンクで3人ぐらいのダイバーが水深20mぐらいまで潜る。もちろん熟練は必要だろうが、一般のC-カード講習よりも少ない時間数で習得できて、安全性はスクーバよりも高いように思える。フィジカルな熟練だけで、あとは何も考えなくても良いから、海鼠採りに集中できる。一人の熟練ダイバーよりも人海戦術のような漁をやっていた。6-7人が漁船に乗っていて、2-3人が交代で次々に潜る。もちろん暖かい海ならではだが。海鼠を採るにはこれが一番効率が良くて安全だろう。もちろん、安全とは比較の問題だから、事故はおこっているだろうが。
旭式マスク、という軽便潜水機がある。浅利熊記という水産講習所(今の東京海洋大学の前身である東京水産大学のさらに前身)の先輩が、自転車の空気入れで潜れる潜水機を目指して開発したマスクである。
今日の昼、このブログを書いたら消えてしまってがっくりきた、書き直しで疲れたので、ここから先は、続く
しかし、多くの機械、道具の進歩の方向は複雑化である。潜水機も同様で、エレクトロニクス、電子化、そして精密化である。そして、その安全保持といえば、精密化された道具が壊れた時に、予備的に使うシンプルな道具にたよる。つまり呼吸期供給を二つの経路から供給する、ツーウエイに頼る。現代のもっとも進んだ潜水機が安全である理由は、二つの方法で呼吸気体の供給を受けられるからである。
機材は複雑化し、高価になり、複雑化しただけ故障の可能性が高くなり危険度が増す。そしてどんどん重くなる、複雑化と重量は正比例する。
今、スポーツリブリーザーが注目を集めている。僕が手に取ってみたのは一種類だが、やがてもう一種類、さらに増えてゆくと思う。それぞれ高価であり、危険については、二つの給気原を持って行くから、安全性は低くないが、重くなり、高価である。例えば、今、40mにスポーツリブリーザーで潜ろうとする。機材とメンテナンス費用、手間、どのくらいかかるのだろう。機材の購入費まで含めれば、年間およそ100万をダイビングのために使える人でないと、できないだろう。僕が、今度のGWに大瀬崎に行くけれど多分、40mまで潜ると思う。普通の空気のスクーバで潜る。それと、スポーツリブリーザーで潜るのとの差は、多分、無減圧で潜れる時間の差だけだろう。僕のオープンサーキットでの40mは、タッチアンドゴーであり、それで良い。
スポーツリブリーザーに反対しているのではない。複雑なシステム、複雑な機構を使いこなすことは、とても面白いし、それは、ダイビングの楽しみの重要な要素であるから、それで良い。つまり、遊びとして楽しく面白い。しかしプロのダイバーが、この機材を仕事に使うことは決してないだろう。だからスポーツリブリーザーなのだ。
プロのダイバーがリブリーザーを使うとすれば、水深60m以上に潜ろうとする時、例えばオープンサーキットのタンクを5本抱えて行くよりは、軽くて、経済性も高いからだ。しかし、それにしても、60mより深く潜る仕事としても、リブリーザーが費用対比効果があるのは、やはり特別なさつえいとか、特別な仕事である。しかし、その特別な仕事でも今のリブリーザーの使い方は、やはりプロ(作業)向きではない。そのことについては、考えがあるので、そのうちに実験してみたいができるかどうか疑問?
プロの潜水機としては、やはり、使用する目的が効率的に達成できて安全性が保たれるならば、シンプルな方が良い。

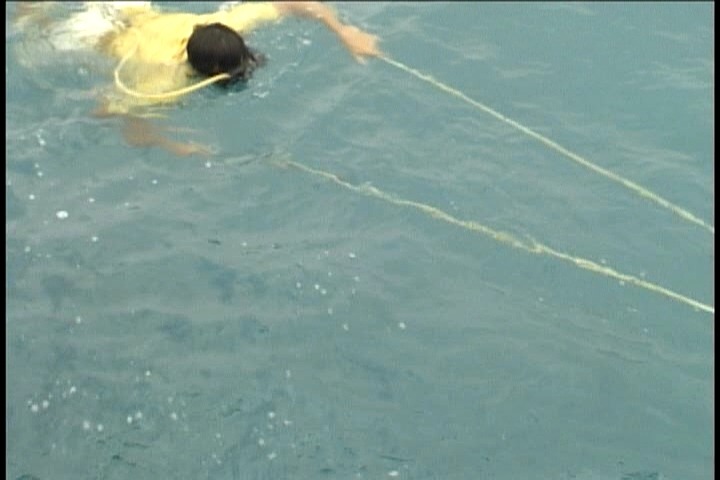



つい最近に紹介したが、インドネシアの海鼠採り漁師は、マスクにホースを突き刺しただけというこれ以上簡単な潜水機はないというくらいシンプルな潜水機を使っている。これで、小さなコンプレッサーと予備タンクで3人ぐらいのダイバーが水深20mぐらいまで潜る。もちろん熟練は必要だろうが、一般のC-カード講習よりも少ない時間数で習得できて、安全性はスクーバよりも高いように思える。フィジカルな熟練だけで、あとは何も考えなくても良いから、海鼠採りに集中できる。一人の熟練ダイバーよりも人海戦術のような漁をやっていた。6-7人が漁船に乗っていて、2-3人が交代で次々に潜る。もちろん暖かい海ならではだが。海鼠を採るにはこれが一番効率が良くて安全だろう。もちろん、安全とは比較の問題だから、事故はおこっているだろうが。
旭式マスク、という軽便潜水機がある。浅利熊記という水産講習所(今の東京海洋大学の前身である東京水産大学のさらに前身)の先輩が、自転車の空気入れで潜れる潜水機を目指して開発したマスクである。
今日の昼、このブログを書いたら消えてしまってがっくりきた、書き直しで疲れたので、ここから先は、続く
















